食品工場の安全対策|労働災害を防ぐ具体策
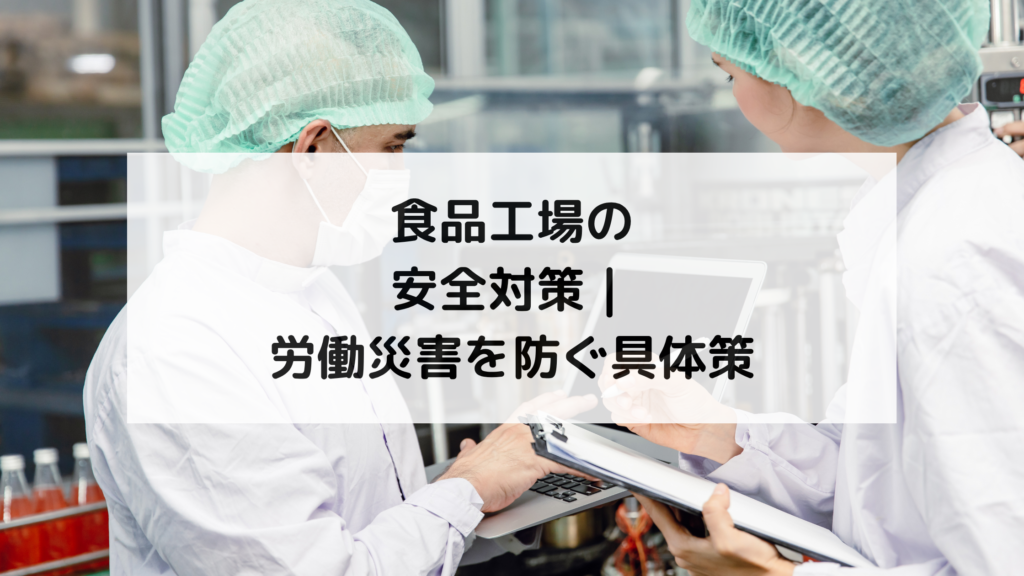
1. 食品工場における安全対策と労働災害の現状

1.1 食品工場で労働災害が多発する理由
食品工場は清潔で管理された環境に見えるかもしれませんが、実際には製造業の中でも労働災害が多い業種のひとつです。特に「はさまれ・巻き込まれ」「転倒」「高温による火傷」など、重傷につながる事故が目立ちます。
厚生労働省の統計では、食品製造業の死傷災害は年間8,000件以上発生しており、全産業平均よりも高い水準で推移しています。
労働災害が多発する主な原因は次のとおりです。
よくある原因とその内容
① 機械との接触リスク
- ミキサー・コンベア・カッターなど、日常的に大型機械を使用
- 点検・清掃中の誤操作による「はさまれ」「巻き込まれ」が多発
- 作業効率を優先して安全装置が無視されることも
② 滑りやすい床環境
- 床の洗浄や調理工程で水や油が広がりやすい
- 滑って転倒、腰や手首の骨折につながるケースが多い
- 清掃タイミングやマット設置が不十分な現場も
③ 多様な作業者の存在
- 外国人スタッフや高齢者の比率が高い
- 言語や文化の違いで安全教育が伝わりにくい
- マニュアルが読めない、標識が理解できないことによる事故も
よくあるシーン:忙しい時間帯の「うっかり」
たとえば朝の出荷前、時間に追われて
- 手袋を省略して作業
- コンベアを止めずに清掃
- 声かけ確認を省略
こうした「いつもの作業」への油断が、重大な災害を引き起こすきっかけになります。
食品工場では「人」「設備」「環境」が絡み合うことで、予想以上に事故のリスクが高くなっています。
1.2 安全対策が不十分なことで起こるリスク
食品工場での安全対策が甘いと、思わぬトラブルが次々に発生します。事故が発生すれば、けが人が出るだけでなく、生産ラインの停止や出荷遅延など、経営に直結する大きな損失にもなります。
特に以下のような問題が起こりがちです。
不十分な安全対策による主なリスク
① 労働災害による人手不足
- けがをした従業員の離脱で、現場の作業バランスが崩れる
- 経験の浅い人への急な引き継ぎで、さらに事故リスクが増加
- モチベーション低下や離職にもつながる
② 生産ラインの一時停止
- 事故発生後は、原因調査や安全確認が必要
- 半日〜数日レベルでラインを止めるケースも
- 出荷スケジュールに大きな影響を与える
③ 企業イメージや信頼の低下
- 労災発生はニュースやSNSで拡散されやすい
- 「安全対策が甘い会社」という印象が定着
- 従業員の採用難や取引先からの見直しにも発展しかねない
たとえば、衛生区域で機械事故が起きてしまった場合。部品の混入や清掃の遅れから、異物混入や衛生基準違反にもつながることがあります。これは製品の廃棄だけでなく、リコール対応が必要になることもあり、損害は想像以上に大きくなります。
こんな失敗が多いです
- 「忙しいから」と安全チェックを省略
- 設備が古いまま放置していた
- 定期教育をやったつもりで記録だけ残していた
こうした油断や慣れが、「防げたはずの事故」を引き起こしてしまうのです。
安全対策が不十分なままでは、労働災害だけでなく、経営や信頼の損失にもつながる危険性があります。
1.3 データで見る労働災害の実態と傾向
食品工場での労働災害は、実際にどのくらい発生しているのでしょうか?感覚的な印象だけでなく、数字で実態を把握することが対策の第一歩です。
厚生労働省や労働基準監督署のデータから見えてくる傾向を整理します。
食品製造業における労働災害の発生件数
- 食品製造業全体での年間死傷災害件数:約8,000件以上
- 製造業全体に占める割合:約15%前後
- 中小規模の工場での発生率が特に高い
特に中小規模の食品工場では、安全衛生の人員や予算が十分に確保されていないことが多く、日常的なヒヤリハットが放置されやすい傾向にあります。
よくある災害の種類と割合
以下は、食品工場における代表的な災害の内訳です。
| 災害の種類 | 発生割合(目安) | 主な原因例 |
| はさまれ・巻き込まれ | 約30% | 機械の点検・清掃中の誤操作など |
| 転倒 | 約25% | 床の水・油による滑り、段差の見落とし |
| 切創・擦過傷 | 約15% | 包丁・刃物・作業中の接触など |
| 墜落・転落 | 約10% | 高所作業、脚立使用時のバランス崩れ |
| 火傷・熱中症 | 約5% | 加熱機器の使用、作業場の温度環境 |
※数値は統計的傾向に基づく概算
よくある背景要因
- 不安全な行動:作業者の確認不足や省略行動(約30%)
- 不安全な状態:設備や環境の不備(約50%)
- その他:教育不足、疲労、連携ミスなど(約20%)
特に注目すべきは、不安全な状態が事故の約半数を占めるという事実です。これは、日頃の点検・整備・ルール化が大きく影響していることを示しています。
傾向まとめ
- 事故は「突発的なもの」ではなく、日々の積み重ねから起こる
- 中小工場ほど安全体制が脆弱で、事故率が高まる
- 教育や仕組みづくりで、事故の6〜7割は防げる可能性がある
数値を見ると、労働災害は「偶然の事故」ではなく、「防げる問題」であることがはっきりわかります。
2. 食品工場で特に多い労働災害の種類と特徴

2.1 「はさまれ・巻き込まれ」事故の特徴と対策
食品工場で最も多い労働災害のひとつが、「はさまれ・巻き込まれ」事故です。特に製造機械が多く稼働する現場では、全体の3割近くをこの事故が占めるという統計もあります。
具体的なリスクとその対策を確認していきましょう。
主な発生シーン
- コンベアやミキサー、カッターの点検・清掃中
- ベルトやチェーン、回転部分に近づいたとき
- 作業中に衣類や手袋が機械に巻き込まれたとき
- 複数人が操作する中で、声かけ確認を忘れたとき
作業者が「止まっていると思っていた」「安全装置が効いていると思っていた」といった思い込みや確認不足が事故を招くケースが多く見られます。
よくある失敗例
- 機械を止めずにそのまま掃除をしてしまう
- 安全カバーを外したまま稼働させる
- 作業中に袖口や軍手が機械に接触してしまう
- 「一瞬だけだから」と安全手順を省略してしまう
こうした行動は、経験年数に関係なく発生します。慣れた作業員ほど危険に気づかず、油断してしまう傾向が強いことも指摘されています。
効果的な対策ポイント
事故を未然に防ぐには、以下のような対策が有効です。
- 作業前に必ず機械の電源を切るルールを徹底する
点検・清掃時は、主電源を切るだけでなく「ロックアウト・タグアウト(誤作動防止措置)」の仕組みが重要です。 - 安全装置・インターロックの点検と定期的な整備
安全カバーが外れていると作動しない設計など、構造的に事故を防ぐ工夫が不可欠です。 - 服装・保護具の確認とルール化
長袖・ゆるい作業着・指先の出た手袋などは巻き込まれの原因になります。服装マニュアルを現場で共有することが重要です。 - 作業時の「指差し呼称」や「声かけ確認」
単純な行動ですが、事故を防ぐ「最後の防波堤」になります。
たとえば、朝の稼働前点検の時間に「電源オフ・カバー確認・声かけ」の3ステップを習慣づけるだけでも、巻き込まれ事故を大きく減らすことができます。
「はさまれ・巻き込まれ事故」は、ルールと設備で防ぐことができる災害です。現場全体で危険への意識を高めることが何より大切です。
2.2 転倒・滑り事故を防ぐための工夫
食品工場では、床の水分や油分が原因で「滑って転ぶ」事故が非常に多く発生しています。特に洗浄作業が頻繁な現場では、転倒による骨折や捻挫が労働災害の約4分の1を占めているともいわれています。
一見軽そうに見える転倒事故ですが、長期離脱や後遺症に繋がるケースもあり、軽視できない重大リスクです。
よくある転倒事故のパターン
- 床の水たまりや油に足を取られて転倒
- 段差や敷居につまずいて転ぶ
- 濡れた床を急いで移動して滑る
- 夜勤中や暗がりで足元が見えずつまずく
とくに、作業に集中しながらの移動や、重いものを持っての歩行中など、視線が下に向かない場面での転倒が多くなります。
転倒が招く被害
- 腰・膝・手首の骨折、靭帯損傷
- 生産ラインからの長期離脱
- 労災認定による保険手続き・休業補償
- 職場内の士気低下や不安感の拡大
たとえば、調理エリアから包装エリアにトレイを運ぶ途中で足を滑らせた場合、製品の落下や破損、異物混入のリスクも生まれることになります。
転倒を防ぐ工夫ポイント
現場でできる具体的な転倒防止策はこちらです。現場でできる具体的な転倒防止策はこちらです。
- 滑りにくい床材・防滑シートの導入
- 水を弾く素材や凹凸のある構造で滑りを軽
- 特に入口付近や洗浄ラインに有効
- 作業靴の選定と管理
- 靴底のグリップが強く、水や油に強い素材を使用
- 定期的に靴底の摩耗チェックを実施
- こまめな清掃とモップの配置
- 水や油がこぼれたらすぐ拭き取れる体制を整える
- 「気づいたらすぐ拭く」文化を全員で共有する
- 段差の解消と色分け表示
- 小さな段差にも明るい色でラインを引いて注意喚起
- スロープ化や安全マットでつまずき防止
- 作業導線の見直し
- 狭すぎる通路、障害物が多いルートは転倒リスクが高い
- 荷物運搬ルートをシンプルに整備する
「濡れている床は危ない」と頭でわかっていても、毎日の作業で慣れてしまうと油断が生まれます。
だからこそ、環境を整えることと、気づいたらすぐ行動できる文化づくりがカギです。
2.3 高温・薬品などによる火傷や化学災害への備え
食品工場では「加熱・洗浄・消毒」といった工程が多く、火傷や薬品による化学災害が起こりやすい環境にあります。これらの災害は発生件数としては少ないものの、被害の深刻度が高く、長期治療が必要になるケースも少なくありません。
よくある火傷・薬品災害のシーン
- 熱湯や蒸気に皮膚が触れてしまう(加熱釜・スチーム調理中など)
- 清掃中に高温の洗浄水を扱っていて手や腕に飛散
- 強い酸性・アルカリ性の洗剤や漂白剤の扱いミス
- ラベルの貼り間違いで誤った薬剤を使用してしまう
特に多いのが、「高温になっていることに気づかない」ケース。透明な蒸気や静かな加熱機器など、視覚的に危険が伝わらない環境が災害の原因になります。
火傷・化学災害のリスク
- 皮膚の水膨れ・深部損傷(重度のやけど)
- 薬品の誤使用による中毒症状や化学反応事故
- 目に入った場合は視力障害につながることも
- 急を要する応急処置が遅れると後遺症のリスクが高まる
たとえば、漂白剤を薄めずに使ってしまい、有毒ガスが発生したことで作業エリアを一時封鎖する事態も起こり得ます。
効果的な対策ポイント
- 高温エリア・薬品使用場所を明確に区分けする
- 区画を色分けし、視覚的に「危険」とわかる表示を徹底
- 作業内容に応じた区域管理で、誤侵入や混乱を防止
- 保護具の常時着用ルールを定着させる
- 耐熱手袋、フェイスシールド、防水エプロンなどを標準装備
- 「使いやすさ」や「着け心地」に配慮しないと形骸化しやすい
- 薬品の保管・ラベル管理を厳格にする
- 原液・希釈液のボトルを色や形で分けて明確に識別
- 毎日の点検と使用記録を簡易的に運用する方法も有効
- 火傷・薬品災害時の応急処置マニュアルを全員で共有
- 何を使い、どの順で処置するかを壁に貼って常時可視化
- 毎年1回以上の訓練で、反射的に動けるようにする
高温や薬品の災害は、一瞬の油断と「知らなかった」が大きなケガに直結します。
だからこそ、教育と見える対策、そして定期的なリマインドが重要なんです。
3. 食品工場で実施すべき基本的な安全対策

3.1 作業エリアの5S徹底で事故を防ぐ
食品工場における安全対策の基本中の基本が「5Sの徹底」です。5Sとは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取った活動で、これを習慣化することで、事故を防ぐだけでなく、作業効率や品質管理にも大きく貢献します。
食品工場では、原料や機材、作業動線が複雑になりがちです。5Sができていないと、つまずき・転倒・誤操作・異物混入など、労働災害の温床になってしまいます。
5Sが不十分な現場で起きやすい事故
- 通路に置きっぱなしの荷物につまずいて転倒
- 散乱した備品に足を取られ、機械に巻き込まれる
- 道具の置き場が定まっておらず、慌てて探すうちに事故発生
- 廃棄物がそのまま放置され、異臭や虫が発生
「忙しいから」「ちょっと後で」が積み重なると、その瞬間が事故の引き金になります。
安全を守る5Sの実践ポイント
5Sを実際の現場に定着させるには、次のような工夫が有効です。
- 【整理】要・不要を分けて、いらないものを排除する
- 使用頻度の低い道具や古い資材を定期的に見直す
- 一時置き場が常に散らかっている場所は事故リスクが高い
- 【整頓】使うものをすぐ取り出せるように配置する
- 備品や道具を「使う順・使う場所」で区分けしておく
- ラベルや色分けで誰でもわかる配置にする
- 【清掃】常に掃除しやすい状態を保つ
- 水や油を放置しない体制をつくる
- 掃除道具を取り出しやすい位置にまとめておく
- 【清潔】設備・床・手洗いエリアの衛生を維持する
- 毎日の清掃ルーチンを時間帯別に設定
- 汚れたらすぐ対応する仕組みを作る
- 【しつけ】ルールを守る意識を全員で育てる
- 定期的な5S教育と現場チェックを組み合わせる
- できていない箇所はすぐフィードバックする
たとえば、通路の脇に置いてあった段ボールひとつ。それが作業員の足に当たり、バランスを崩して転倒、となれば大きな事故になります。
5Sは「当たり前だけど、つい後回しにしがちな習慣」を形にする仕組みです。
毎日数分の意識で、事故の芽を根本から摘み取ることができます。
3.2 保護具の着用ルールと点検方法
保護具の使用は、事故を防ぐための最前線です。
ただし、「着けていれば安心」ではなく、正しく使う・点検することが大事です。
よくある失敗例
- 手袋がサイズ不適切で作業中に外れる
- ヘルメットが劣化していて衝撃を防げない
- 面倒だからと保護眼鏡を外して作業する
対策ポイント
- 用途別に保護具を明確に分類(手袋、メガネ、防音具など)
- 定期点検の仕組みを作る(週1回のチェック+交換基準の設定)
- 保護具の保管場所を決めて整頓
- 着用状況を現場リーダーが随時確認
- 正しい着用方法を写真付きで掲示
ルールがあっても徹底されなければ意味がありません。日々の習慣づけがカギです。
3.3 安全装置と緊急停止機能の導入ポイント
機械トラブルによる事故を防ぐには、安全装置と緊急停止機能の整備が不可欠です。これらがない現場では、万が一のときに大事故につながります。
よくある見落とし
- 緊急停止ボタンが遠くて押せない位置にある
- インターロック装置が故障したまま使われている
- 装置の存在を知らない作業者がいる
導入と運用のポイント
- すべての機械に非常停止ボタンを設置(目立つ赤色で統一)
- カバーを外すと自動停止するインターロック機能を導入
- 装置の動作テストを月1回以上実施
- ボタンやセンサーに異常がないか点検記録を残す
- 新入社員向けに「安全装置の使い方」を研修に組み込む
設備トラブルは想定外のタイミングで起きます。装置の整備と教育が事故を防ぐ要です。
4. 人的ミスを防ぐ教育・訓練の仕組みづくり
4.1 新人・外国人スタッフ向け教育の工夫
労働災害の多くは、入社間もない人や外国人スタッフに集中しています。教育が不十分だと、ルールの認識不足から事故が起こりやすくなります。
よくある教育の課題
- 専門用語が多く、内容が伝わらない
- 教えたつもりでも理解されていない
- 「見て覚える」だけでマニュアルが機能していない
教育を強化するポイント
- 写真・動画を使った視覚的なマニュアルを用意
- 母国語対応の資料を導入(特に注意喚起・禁止事項)
- 実技中心のOJTで体に覚えさせる
- 「確認テスト」を取り入れて理解度チェック
- 先輩社員によるメンタリング体制の構築
新人や外国人が安心して作業できる環境づくりが、事故ゼロへの第一歩です。
4.2 ヒヤリハットの共有と事故予防意識の定着
大きな事故の前には、小さな「ヒヤリハット」が必ず起きています。
この“気づき”を共有する文化があるかどうかが、安全管理の質を大きく左右します。
よくある課題
- 小さなミスを報告しにくい職場雰囲気
- 「報告しても変わらない」と思われている
- 共有しても活用されず、形式だけで終わっている
意識定着のポイント
- ヒヤリハット報告を匿名でも提出可能にする
- 毎朝5分、1件だけでも共有する時間をつくる
- 実際に起きたヒヤリを「ポスター化」して掲示
- 報告があった場合、現場改善につなげるフィードバックを即実施
- 「報告ありがとう」の声かけで報告意欲を育てる
ヒヤリの共有は、職場全体の安全意識を底上げするチャンスです。
4.3 年次訓練・多言語対応などの持続的取り組み
安全教育は一度教えたら終わり、ではありません。継続的な訓練と多様な人材への対応が不可欠です。更新されない知識は、時間とともに形骸化してしまいます。
よくある問題点
- 教育が入社時だけで終わっている
- 外国人スタッフ向けの対応が不十分
- 訓練が形式的で現場の実態と合っていない
持続的な取り組みのポイント
- 年1〜2回の避難訓練・応急処置訓練を実施
- 多言語化されたマニュアルや注意表示を用意
- VRや動画教材など、参加型の教育ツールを活用
- 作業内容ごとに定期的な再教育を行う
- 教育記録を残して更新状況を見える化
習慣的な訓練と多様性への配慮が、安全文化の定着に直結します。
5. 安全対策の仕組み化で労働災害を根本から防ぐ
5.1 リスクアセスメントの具体的な進め方
リスクアセスメントは、労働災害を防ぐための「見える化」ツールです。作業に潜む危険を洗い出し、評価・対策を行うことで、事故の芽を摘み取れます。
ありがちな問題点
- 危険の洗い出しが「感覚」頼りで曖昧
- 評価基準がバラバラで優先順位がつけにくい
- 対策を立てても実行や記録がされていない
進め方の基本ステップ
- 作業ごとに「危険源」を抽出(機械・動作・環境など)
- 「発生頻度」と「重篤度」でリスク評価
- 優先順位をつけて対策を検討・実行
- 改善策の効果を定期的にモニタリング
- チェックシートや写真で記録を残す
現場の声をもとに、実行可能な対策を選ぶことが成功のカギです。
5.2 HACCP・ISO45001の考え方を現場に活かす
食品工場では、HACCPやISO45001に基づく安全管理が求められます。これらは単なる認証取得ではなく、現場改善に直結する仕組みとして活用することが大切です。
よくある誤解・課題
- 書類対応が目的になってしまい、実際の改善につながらない
- 現場の作業者が内容を理解していない
- 認証取得後の見直しや運用が止まっている
現場への落とし込みポイント
- ●HACCPの「危害要因分析」で工程の危険を明確化
- ●ISOの「PDCAサイクル」で安全対策を定期的に改善
- ●現場リーダーが手順書をかみ砕いて教育に活用
- ●ルールの「なぜそうするのか」を共有することが重要
- ●定期的な内部監査で形骸化を防ぐ
制度を“動かす”のは現場です。理解と納得がなければ意味がありません。
5.3 外部専門機関による支援の活用方法
自社内だけで安全対策を完璧に整えるのは難しいものです。外部の専門機関を活用することで、客観的な視点と専門ノウハウを得ることができます。
よくあるつまずきポイント
- 自社だけで考え込み、改善が進まない
- 対策が場当たり的で、再発を防げていない
- 法令や基準の変更に対応しきれていない
外部支援の活用ポイント
- リスクアセスメントや安全教育の見直し支援
- HACCPやISO取得に向けたマニュアル整備
- 事故発生後の原因分析と再発防止対策の立案
- 現場巡回による第三者視点での改善提案
- 法令対応や記録管理のアドバイスも可能
専門家と一緒に対策を進めることで、安全対策は一段と実効性のあるものになります。
6. まとめ:食品工場の安全対策は仕組みと習慣がカギ
安全対策は一度実施すれば終わり、ではありません。
日々の業務や環境の変化に合わせて継続的に見直すことが大切です。
よくある誤解・課題
- 一度決めたルールを更新せず放置
- 事故がないと安心して対策を怠る
- 新しい機械や作業が増えても対応しない
継続的な安全対策のポイント
- 定期的なリスク評価と改善計画の更新
- 作業者からのフィードバックを取り入れる仕組み
- 新規導入設備や工程変更時の安全確認
- 教育・訓練の定期的な実施と内容のブラッシュアップ
- 現場リーダーが主体的に安全管理を推進
安全対策は“習慣化”が成功のカギ。継続的な努力が事故ゼロを実現します。
食品工場の安全管理なら、TMTユニバーサル株式会社へお任せください
労働災害を未然に防ぐためのリスクアセスメントや教育訓練、最新の安全装置導入までトータルにサポートします。
安心で効率的な現場づくりを目指すならぜひご相談ください。
まずはTMTユニバーサル株式会社のホームページをご覧ください。
- 関連タグ
- 安全対策

 CONTACT
CONTACT